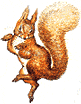
http://new-party-9.net/archives/2274
2015年7月21日 天木直人のブログ 新党憲法9条
きょう7月21日の朝日新聞の社説を見て驚いた。
ついに書いた。
あの砂川判決の裏には歴史の暗部があると。
当時の田中耕太郎最高裁長官は、あの判決を下す前に駐日米国大使らと会って裁判情報を伝えていたことが米政府の公電の公開で明らかになったと。
だからこそ、当時の被告が裁判のやり直しを求めた再審請求を起こしていると。
そして、その再審請求裁判が終盤を迎えていると。
いまこそ司法はみずから史実を検証し、国民の疑念にこたえるべきであると。
ここまで書いた朝日の社説は、実はものすごい社説なのだ。
まさしく我々が訴えてきたことだ。
砂川判決の裏にあったこの国の司法の対米従属ぶりが白日の下にさらされ、一人でも多くの国民が史実を知るようになれば、すべてが根底から覆る。
砂川判決で有罪とされた被告らの名誉が回復されるだけではない。
安倍首相や高村自民党副総裁が安保法制案の合憲の根拠としている砂川判決の正当性がが否定され、安保法制案の議論そのものが白紙に戻る。
日米同盟の正当性がゆらぐ。
だからこそ、メディアは意図的に砂川再審請求訴訟の事を報じなかったのだ。
6月18日に、土屋源太郎さんら被告がわざわざ記者会見を開いて砂川判決の不当さを訴えたのにメディアは無視した。
ところがついに朝日新聞が書いた。
しかもその社説で正面から田中耕太郎最高裁長官の対米従属ぶりを批判し、砂川判決再審請求訴訟に、司法が歴史の検証を行え、とまで要求したのだ。
日米同盟を最優先する朝日新聞がここまで社説で書くとは私は思わなかった。
だから衝撃的なのだ。
朝日新聞を読売新聞以上に対米従属的だと批判してきた私は、その批判を撤回し、朝日新聞の勇気を讃えたい。
司法は朝日新聞の社説が求めているように、みずから歴史の公正な審判者とならなければいけない。
東京地裁で行われている砂川判決再審査請求裁判は、土屋さんらが8月7日までに最終意見書を提出して審理は結審することになっているという(7月16日東京新聞)
おりから安保法制案の国会採決が近づいている。
東京地裁は、司法は政治的判断を下さないなどと言って、判決をいたずらに遅らせたり、逃げたりすることは許されない。
国民は砂川判決再審査請求裁判の行方から目を離してはいけない(了)
◇
砂川判決―司法自ら歴史の検証を
http://www.asahi.com/paper/editorial.html?iref=comtop_gnavi
2015年7月21日(火)付 朝日新聞社説
最高裁は、憲法の番人と呼ばれる。行政から、立法から、そして言うまでもなく外国政府から独立した存在であることが、司法の公正さの礎である。
ところが半世紀前、その原則を揺るがす出来事があった疑いが今も未解明のままだ。「砂川判決」の背後にある米政府と最高裁長官との関係についてで、当時の被告が裁判のやり直しを求めた審理が終盤を迎えた。
司法は自ら史実を検証し、国民の疑念にこたえるべきだ。
1957年、米軍基地の拡張に反対するデモの学生らが、刑事特別法違反に問われた。
2年後、日米安保条約の改定を前に世論が盛り上がるなか、東京地裁は「米軍駐留は憲法9条違反」として無罪を言い渡した。だが9カ月後、最高裁は破棄し、差し戻した。
日米安保条約のような高度に政治的な問題について司法は判断しない。いわゆる「統治行為論」を最高裁判決は打ち出し、今も重い影響力をもっている。
この判決をめぐる疑義が明るみに出たのは2008年以降。裁判当時の田中耕太郎最高裁長官が駐日米大使らと判決前に会い、裁判の情報を伝えていたとの米政府の公電が公開された。
条約改定を進めたい日米両政府にとって「米軍駐留は違憲」との一審判決がいかに不都合だったかは、想像にあまりある。
米大使館の公電によると、大使に対し長官は一審判決は誤っていたとし、最高裁では全員一致で判決して「世論を乱す少数意見」は避けたい、との望みを語った。
政府高官も無関係ではない。一審判決の翌朝、外相に会った大使が判決を「正す」重要さを強調したとの文書もある。
「公平な裁判を受けられなかった」と被告や遺族が昨年、再審を請求したのは当然だろう。
公電は外交担当者の見方によるものとはいえ、複数の公電が伝える長官と高官らのふるまいは、司法の独立だけでなく、国家の主権すら忘れ去られていた疑念を抱かせる。
それは敗戦の影が色濃く残る往時の出来事とは決して片付けられない現代の問題である。米軍基地問題の訴訟をめぐり、統治行為論は、住民被害の救済を阻む壁であり続けている。
さらに安倍政権は、今国会での成立をねらう安保関連法案の合憲性の根拠として、砂川判決を挙げた。その歴史的検証はいよいよ不可欠である。
憲法をめぐる議論は活発になっている。国民の信頼を得るには、最高裁はこの歴史の暗部から目を背けてはならない。