http://www.asyura2.com/12/senkyo134/msg/104.html
投稿者 赤かぶ 日時 2012 年 8 月 06 日 05:16:51: igsppGRN/E9PQ
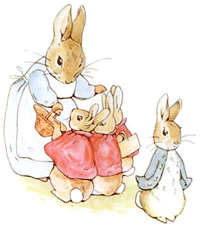
「2012年と1960年 国民の怒りが政権を打倒する日」対談・孫崎享氏×高橋洋一氏×長谷川幸洋氏
http://ameblo.jp/heiwabokenosanbutsu/entry-11321286650.html
週刊ポスト2012/08/17・24号 :平和ボケの産物の大友涼介です。
(※参考)はブログ主が勝手にリンクしました。(※①~③)は雑誌に元々あったものです。
デモが国会議事堂前を占拠する光景は、52年前と同じだった。
7月29日、20万人ともいわれる人々が国会を取り囲み、原発再稼働反対のキャンドルを灯した。1960年、国会前には日米安保条約に反対する数十万人の学生デモ隊が押し寄せ、時の岸信介内閣は退陣に追い込まれた。
鉢巻き姿の活動家はいなくなったが、ベビーカーを押す母親や麦藁帽子の老人は、確かに声を上げている。この熱は、あの時と同じく政権打倒へ結びつくのか。
外交、霞が関、メディアを知り尽くす3氏が、”革命前夜”にある「1960年と2012年の日本」をテーマに論じ合った。
■間接民主主義への不信感
週間ポスト:今回のデモと60年安保闘争をどう比較するか。
孫崎:60年安保は組織化されていた。学生は用意されたバスや電車でデモに行き、労働者は組合活動として参加し、新聞などのメディアも支援していた。ある意味では反体制という体制に乗せられていたんです。一方、今のデモは、原発再稼働反対から始まって、何かおかしい、日本を動かしているものが何か違うぞ、と個人が判断している。だから1人1人が地下鉄でふらっと来て、デモに参加してふらっと帰っていく。かつてのように熱に浮かされたという感じではない。
参加者はどちらかというとクールで、誰かに動かされることを最も嫌う人たちが個人の判断で加わり、発言していく。デモという形式は同じでも、何者かに操作されているのではなく、動かしている力が個人個人の判断なので、この流れはどこかで打ち切りになることはないと思います。
高橋:アラブ諸国で起きたジャスミン革命と似ているところはある。ネットで繋がるので、誰でもアクセスできて情報発信もできる。国民にすれば、選挙で選ばれた議員が政治を行うという間接民主主義が民意を吸い上げなくなって、期待できない。加えて国民はマスコミから間接的な情報を与えられているが、その情報も信用できない。国民の代理人である政治家も官僚もメディアも、みんな嘘つきだってバレちゃった。だからやむを得ず直接的な行動に出るしかなくなったのではないか。
ただ、目的達成のためには、最終的には選挙しなければいかんともし難いわけです。果たして彼らは選挙に行くのか。そこが僕にはまだわからない。
長谷川:僕はデモを毎週取材していますが、目立つのは若者より60歳以上の高齢者です。60年安保や70年安保を知っている世代ですね。年配男性の中には、昔こんなことがあったよな、ということを知っている人たちもいる。
それから女性が多い。お母さんたちは子どもの安全をどうしてくれるのかって、本当に怒っている。おそらく安保のときはデモに参加しなかった年配女性もいるが、「ここで私が原発に何か言わなければ若いお母さんたちに申し訳ない」という思いを持っている。
高橋:長谷川さんは学生運動やっていたから血が騒いでいるんじゃない?
長谷川:もっと原理的に考えてますよ(笑)。政治とは議員バッジをつけた人がやることだとみんな思っていた。新聞の政治面も政党と国会議員の話が主でしょう。だけど本来、政治は「普通の人々」がするものですよ。
今回のデモを契機に、「オレたちの声を聞け、主役は国民であり、政党や議員は代理人に過ぎない」と、国民が政党や議員から政治を取り戻す認識のパラダイム変化が起きるかもしれない。鳩山由紀夫元首相がデモに来たとき、「どうせ人気取りだ」「CO2削減をいって原発を増やそうとした張本人じゃないか」というステレオタイプの批判が出たけれども、私から見ると、国民が街頭に元総理を呼び出して、「官邸に行って国民の声を野田総理に伝えろ」と代理人として使いに出すという現象が起きたともいえる。それが非常に面白いところで、これからの政治の形を示しているんじゃないかと思う。
■反体制の意思表示はデモ以外にも
長谷川:ただひとつ気になるのは、7月29日の国会包囲からデモの様子が変わる懸念もある。全共闘とか、全学連とかの旗が出てきて、「車道を空けろ」と議事堂前の車道を占拠した。人々はデモを乗っ取ろうという組織的な動きに触発されたかもしれない(※参考)。私も学生運動やっていたからよくわかる(笑)。彼らは挑発行為を徐々にエスカレートするはずです。そうなると当局がデモを潰す口実にされかねない。
※参考 長谷川幸洋氏(8/3深夜~)「8月3日の再稼働反対抗議行動に参加してあらためて気づいたことがあった」 http://togetter.com/li/350061
高橋:当局が出てくる前に、一般の人が参加しなくなる。一般の人がいなくなれば、グループ(反原発団体)の運動になってしまう。
孫崎:私はそれでも国民の行動は消えないと思いますよ。官邸デモというのはほんのひとつの表現であって、すべてではない。60年安保は、ピークの時に新聞7紙が「暴力革命を排し議会主義を守れ」という異例の共同宣言(※①)を出した結果、騒動が収まり、国会前から一般人が消えて潰れてしまいました。
※① 1960年6月17日、新聞7紙が「その理由の如何を問わず、暴力を用いて事を運ばんとすることは、断じて許されるべきではない」との7社共同宣言を発表。宣言を書いたのは、対米終戦工作に関わった経験を持つ笠信太郎・朝日新聞論説主幹だった。
だけど今回は、官邸デモがなくなっても、国民は別の方法で意思を表明すると思う。デモだけが表現する手段ではない。
長谷川:60年や70年安保と決定的に違うのは、福島原発事故で国土の3%が事実上失われ、放射能で故郷に住めなくなった10数万人の”さまよえる人々”が厳然と存在していること。この人たちがいる以上、運動の火は絶対消えない。メディアも見捨てない。
週刊ポスト:60年安保は岸内閣を倒した。ならば、今回の行動も政権を倒すところにつながっていくのか。
高橋:どこまで運動が広がるかにもよるが、民意の受け皿はなくはない。民主、自民以外の政党や政治家でしょう。それは橋下徹(大阪市長)かもしれない。橋下さんたちがエネルギーをどうやって吸収していくか次第でしょうね。
孫崎:60年は打倒岸内閣という政治目的があって動いていたけれども、今は個人が再稼働反対を言わなければならないという自己表現でやっているから、最終的に政権を倒すとか、ある種の政治目的を達成しなければならないとまでは考えていないと思う。しかし、一般の国民が参加することによって、これまで黙っていた人々に影響を与えていくわけです。私たちもそうでしたが、反体制の意思表示をすることには恐さがある。それが今回のデモで、恐くない、意思表示していいんだ、というきっかけになった。
■安保闘争は従米派に利用された
略
■「米国の意向」を捏造する官僚
略
■60年安保体制からの「脱」
週刊ポスト:60年安保では新聞7社の共同宣言がデモを潰した。メディアが国民を向いていないのは今も同じで、「決められる政治」といって野田首相の原発再稼働や消費増税を後押ししている。
高橋:そもそも国民の困ることを何のチェックもないまま決めているのに、「決められる政治」と持ち上げるのはおかしい。選挙で問うてから決めるべきでしょう。原発再稼働も野田政権は当初、事故調査をやって、原子力規制庁をつくってから判断すると言っていたのに、何もしないうちに素人である4閣僚で決めた。
長谷川:新聞がいっせいに社説で「決められる政治」と書いたのには裏があるんです。「決められない政治からの脱却」というキャッチフレーズが最初に出たのは、今年1月の施政方針演説。各紙の足並みが揃ったのは、財務省が論説懇(論説委員との懇談会)で完璧にレクチャーしたからだと思います。
高橋:論説委員は財務省のポチの典型ですね。私も課長のときに、各紙の論説委員を回ってレクしていたが、同じ情報を流しても記事に濃淡が出る。そうすると上から「レクが不十分だったんじゃないか」と怒られるわけ。それで論説に、「ここが違っている」と注意する。結果的に濃淡さえも全く同じ「財務省のリリース」が紙面に載る。
長谷川:メディアは公正、客観的な報道だとか、真実の追求なんていうけど、役所にすれば情報操作の対象でしかない。
高橋:当たり前じゃない。こっちが流した情報をそのまま書くんだから。
略
長谷川:はっきり言って、新聞の経済記者が主計局とケンカして財政の記事を書けるかというと、普通は書けない。逆に、役所のポチになって情報を貰えば、どんどん餌を貰って太っていき、社内で出世もできる。それを断ち切ると記者は生きて行く場所を失う気持ちになる。
高橋:だけど長谷川さんは脱ポチでしょう?私は脱官僚で、孫崎さんは脱米国。そうした「脱」の動きが様々な場所で起こっている。この流れを吸い上げる中間的な存在が出てくれば、変革の可能性はある。
孫崎:そうした仕組みが固まったのはまさに60年安保の後でした。国民が今回のデモによってその仕組みからの脱却を目指しているとすれば、実に興味深い歴史の巡り合わせですね。





















